幼稚園・認定こども園とは
幼稚園とは
家庭は、幼児の成長・発達に最も大切な基本的な環境ですが、幼児の「あれがやりたい」・「これを知りたい」・「友達がほしい」という気持ちに応えられるものとして幼稚園があります。
幼稚園での集団生活の中で、やる気や思いやりが育ち、自立心や協調性が培われ、心身が大きく育ちます。
幼稚園とは、こうした役割を果たす所です。
認定こども園とは
認定こども園は、幼稚園と保育所両方の機能を備えた施設で、教育と保育を一体的に行うところです。教育を希望する(保育の必要がない)お子さまについては、幼稚園・認定こども園のいずれにも入園することができます。
認定こども園の種類
認定こども園には、以下の4つの種類があります。(高崎市には幼保連携型と幼稚園型の園があります。)
| 幼保連携型 | 幼稚園(学校)と保育所(児童福祉施設)としての法的位置づけをもつ単一の施設として認可されたところです。 |
| 幼稚園型 | 認可幼稚園が、保育所的な機能を備えて認定こども園としての機能を果たすところです。 |
| 保育所型 | 認可保育所が、幼稚園的な機能を備えて認定こども園としての機能を果たすところです。 |
| 地方裁量型 | 幼稚園・保育所のいずれの認可もない地域の教育・保育施設が、認定こども園として必要な機能を果たすところです。 |
保育所・認定こども園(保育部分)
保育所や認定こども園(保育部分)は、保護者の仕事や病気等により、0歳から就学前までの保育を必要とする児童が対象となります。幼稚園等とは申し込み方法が異なりますので、保育所や認定こども園(保育部分利用)の利用を希望する場合は、高崎市の保育課・各支所市民福祉課にお問い合わせください。

入園の手続き
高崎市の幼稚園及び認定こども園(幼稚園部分利用に限る)では、9月1日から、翌年度の新入園児の申込みを開始します。詳しくは、各園にお問合わせください。(年度の中途入園の申込みは、随時各園にお問い合わせください。)
新入園児の申込方法・入園資格・選考方法
| 私立幼稚園・認定こども園 | |
| 申込方法 | 9/1から各園で入園願書等の受付を開始します。 募集の詳細は、各園にお問合わせください。 |
| 入園資格 | 各園にお問合わせください。 |
| 選考方法 | 各園にお問合わせください。 |
* 9/1が土日のときは、次の月曜日からとなります。
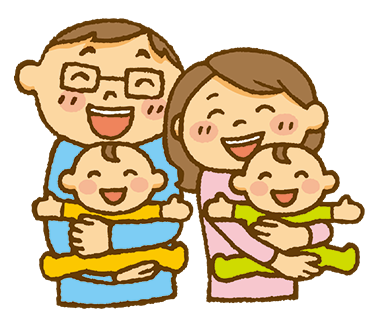
子ども・子育て支援新制度
高崎市の幼稚園の類型(2020.4.1 時点)
認定こども園
| 類型 | 該当施設 |
| 幼保連携型 | みどり・明徳・むつみ・中川・櫻丘・中居・ひばり・国分寺 |
| 幼稚園型 | 佐藤・八幡・こだま・長野・東部文化・ぐんま・堤ヶ岡・上武大附属 |
幼 稚 園
| 類型 | 該当施設 |
| 新制度の幼稚園 | 三山・高崎天使・城南・高南・いちごばたけ・清風・榛名愛育・さわらび |
| 従来制度の幼稚園 | すみれ・健大附属 |
* 次年度以降、各園の判断により類型が変更となることもあります。入園にあたり、最新の状況は各園にお問合せください。
認 定 申 請
認定こども園や新制度の幼稚園を利用する場合は、入園が内定した後、園を通じて市に子どものための教育・保育給付認定申請を行い、市から認定を受ける必要があります。
保 育 料
保育料は、令和元年10月より無償化されました。
幼児教育・保育の無償化について
保 育 料(対象者:全ての園児)
新制度の幼稚園・認定こども園
子ども・子育て支援新制度の仕組みに入る幼稚園と認定こども園の幼稚園利用の保育料は、幼児教育・保育の無償化により、満3歳児から年長までの園児について無料になります。
ただし、給食費や通園送迎費、行事費、父母の会費等は、保護者の負担となります。
従来制度の幼稚園
子ども・子育て支援新制度の仕組みに入らない私立幼稚園(従来制度の私立幼稚園)の保育料は、幼稚園が定める額となりますが、幼児教育・保育の無償化により、満 3 歳児から年長までの園児について月額25,700円を上限に保育料と入園料が無償化されます。
ただし、保育料等に給食費や通園送迎費、行事費、父母の会費などが含まれる場合、給食費等は無償化の対象外ですので、保護者の負担となります。無償化の方法は、保育料については無償化の金額を減免し、入園料については後日償還払いをいたします。
算定のイメージ
| 例 1 | 例 2 | |
| 入園料 | 40,000円 | ー |
| 入園料(月額) | 3,330円 | ー |
| 保育料 | 24,000円 | 24,000円 |
| 無償化対象 | 25,700円 | 24,000円 |
| 実質負担額 | 1,630円 | 0円 |
*入園料(月額)=入園料÷年間在籍月数(10円未満は切り捨て)
(上記例1の入園料(月額)は、40,000円÷12か月≒3,330円)
預かり保育の利用料(対象者:認定を受けた園児)
園児が家庭において必要な保育を受けることが困難であると市から認定を受けた場合に、幼稚園において通常保育時間を超えて、預かり保育を利用すると、幼稚園が実施する預かり保育の利用料が無償化されます。
また、利用している幼稚園の平日の通常保育時間と預かり保育の提供時間の合計が8時間未満又は預かり保育の開所日数が年間200日未満である場合は、月額11,300円(満3歳児は月額 16,300円)から幼稚園における預かり保育の利用料が無償化された額を差し引いた額を上限として、認可外保育施設等の利用料も無償化の対象となります。
保育の必要性の認定
園児が家庭において必要な保育を受けることが困難であると市から認定を受けた場合に、幼稚園において通常保育時間を超えて、預かり保育を利用すると、幼稚園が実施する預かり保育の利用料が無償化されます。
また、利用している幼稚園の平日の通常保育時間と預かり保育の提供時間の合計が8時間未満又は預かり保育の開所日数が年間 200日未満である場合は、月額 11,300円(満3歳児は月額 16,300円)から幼稚園における預かり保育の利用料が無償化された額を差し引いた額を上限として、認可外保育施設等の利用料も無償化の対象となります。
- 1か月に64時間以上仕事をしている
- 妊娠中または出産後である(出産前2か月から出産後2か月まで)
※ 多胎児の場合は、出産前4か月から出産後2か月まで - 病気やけが、または心身の障害による
- 同居または長期入院等の親族の介護・看護にあたっている
(1か月に64時間以上の介護・看護が必要/長期入院等の場合は、同居を問わない) - 火災、風水害、地震等の災害の復旧にあたっている
- 仕事を継続的に探している(3か月まで)
- 学校に在学しているまたは職業訓練を受けている(1か月に64時間以上の就学・訓練が必要)
- 虐待やDVによる
無償化の額
月ごとに「実際に支払った預かり保育の利用料」と「450円×実際に預かり保育を利用した日数」で計算された額とを比較して、少ない方の額が無償化の対象となり、利用料は減免されます。ただし、無償化の上限額は、月額11,300円(満3歳児は月額16,300円)までです。
算定のイメージ
| 例 1 | 例 2 | |
| 利用料 | 4,000円 | 9,500円 |
| 利用日数 | 10日 | 20日 |
| 上限額 | 4,500円 | 9,000円 |
| 無償化対象 | 4,000円 | 9,000円 |
| 実質負担額 | 0円 | 500円 |
申 請 手 続
詳細は、幼稚園を通じてご案内します。
新制度の幼稚園・認定こども園
保育料の無償化については、申請の必要はありませんが、預かり保育の利用料が無償化されるためには、保育の必要性を証明するものを添付して申請する必要があります。
従来制度の幼稚園
幼児教育・保育の無償化には、申請が必要になります。預かり保育の利用料が無償化されるためには、保育の必要性を証明するものを添付して申請する必要があります。

幼稚園・認定こども園ではこんな経験をします
- 友達といろいろな経験をします。
- 協力し合うことの楽しさを実感します。
園で大勢の友達や先生に出会えます。みんなそれぞれ違った個性を持っていますから、わかり合うまにでは時間と努力が必要です。けれども、わかり合い協力し合う中で、ひとりでできない楽しい経験を味わえます。 - 助け合うことの大切さを知ります。
園生活では、自分を相手に合わせて変えなければならない場合もあります。そのような人間関係を通じて子ども達は信頼し合い助け合うことの大切さに気づきます。そして、人は誰でもひとりで生きるだけでなく、助け合いながら生きていくことを実体験を通じて知っていきます。
- 協力し合うことの楽しさを実感します。
- 心身の成長発達を促します。
- 自立心や自発的な態度を養います。
集団生活に入ると、自分のことは自分でするようになり、子どもは次第に自立していきます。同時にいろいろな物事に興味や関心を持ち、意欲を持ってとりくむ態度も少しずつ身に付けていきます。 - 充実感のある経験をたくさんします。
子どもはみずから発見し、好奇心を持っていろいろな物事にとりくみ、工夫したり、解決したり、感動したりしながら充実感を味わっていきます。このような自己充実の機会に多く出会いながら、心身が豊かに育ちます。
- 自立心や自発的な態度を養います。
- 生活の基本やすばらしさを知らせます。
- 社会的なモラルやマナーを学びます。
幼児期に、自然や生命の尊さ、人間尊重、安全のしつけ、基本的な生活の習慣や社会性をしっかりと身に付けることが大切です。園では、健康で安全であるということに加え、社会性・モラル・マナーを身に付けることを大切にします。 - 豊かな感性や心情をはぐくみます。
幼児期には、いろいろな活動をする楽しみや、自分を表現したり創造するよろこびを体験させたいものです。よい自然や人や文化との出会いの中で、豊かな感情や心情をはぐくむよう、園ではつとめます。また、遊びの中でのいろいろな体験を通じて、集中力・意志力・想像力・創造力・社会性などを培います。
- 社会的なモラルやマナーを学びます。
入園前の準備として
子ども達が園生活を気持ちよく始めるためには、基本的な生活習慣は身に付けさせておきたいものです。入園前に準備するしつけと心得は次のようなものです。
-
早寝・早起き
朝、洗面・朝食など生活のリズムにゆとりを持たせ、早寝・早起きをしましょう。 -
食事
朝食は、決まった時間に食べる習慣を付け、好き嫌いなくなんでも食べるようにしましょう。 -
衣服の脱着
衣服の脱着は、自分で脱ぎ着できるようにしましょう。 -
排泄
毎朝、トイレに行く習慣を身に付けましょう。 -
友達
子どもが遊んでいる所で一緒に遊ぶようにしましょう。
こんな事も出来るといいですね
- 自分で顔や手が洗えてふけるように。
- 呼ばれたら「ハイ」と答えたり挨拶が出来るように。
- 持ち物に名前を付け、文字の形やマークで自分のものだと分かるように。
- 遊んだ後の後始末は自分でしましょう。

お母さんに
- しかるよりほめること。
- 子どもの力を信じて時間がかかっても、我慢して待ちましょう。
- 自分で出来たら必ず誉めてあげましょう。
- 情報に左右されたり、神経質になり過ぎないようにしましょう。
